キッチンの背面収納を後から設置しようと考えたとき、「もっと早く考えておけばよかった」と感じる人は少なくありません。収納スペースが足りない、家事動線がスムーズにいかない、見た目がちぐはぐになる――そんな後悔の声の多くは、事前の設計や準備不足に起因しています。
特に注意したいのは、「置けばなんとかなるだろう」という発想で既製品の収納家具を導入してしまうケースです。サイズが合わなかったり、扉の開閉がスムーズにできなかったりといった小さな不満が、日々の生活の中で積もっていきます。
また、キッチンは冷蔵庫やゴミ箱など、もともとスペースを取りやすい設備が多いため、単純に収納を「足す」だけではかえって使い勝手を悪くしてしまうこともあります。
後悔しないためには、設置の前に「なぜ収納が必要なのか」「どの位置が適しているのか」「使い勝手はどう変わるのか」を丁寧に考えることが欠かせません。焦らず、生活動線や空間のバランスまで含めて検討することが、納得のいく後付け収納への第一歩となります。
どこに注意すれば“使える”収納になる?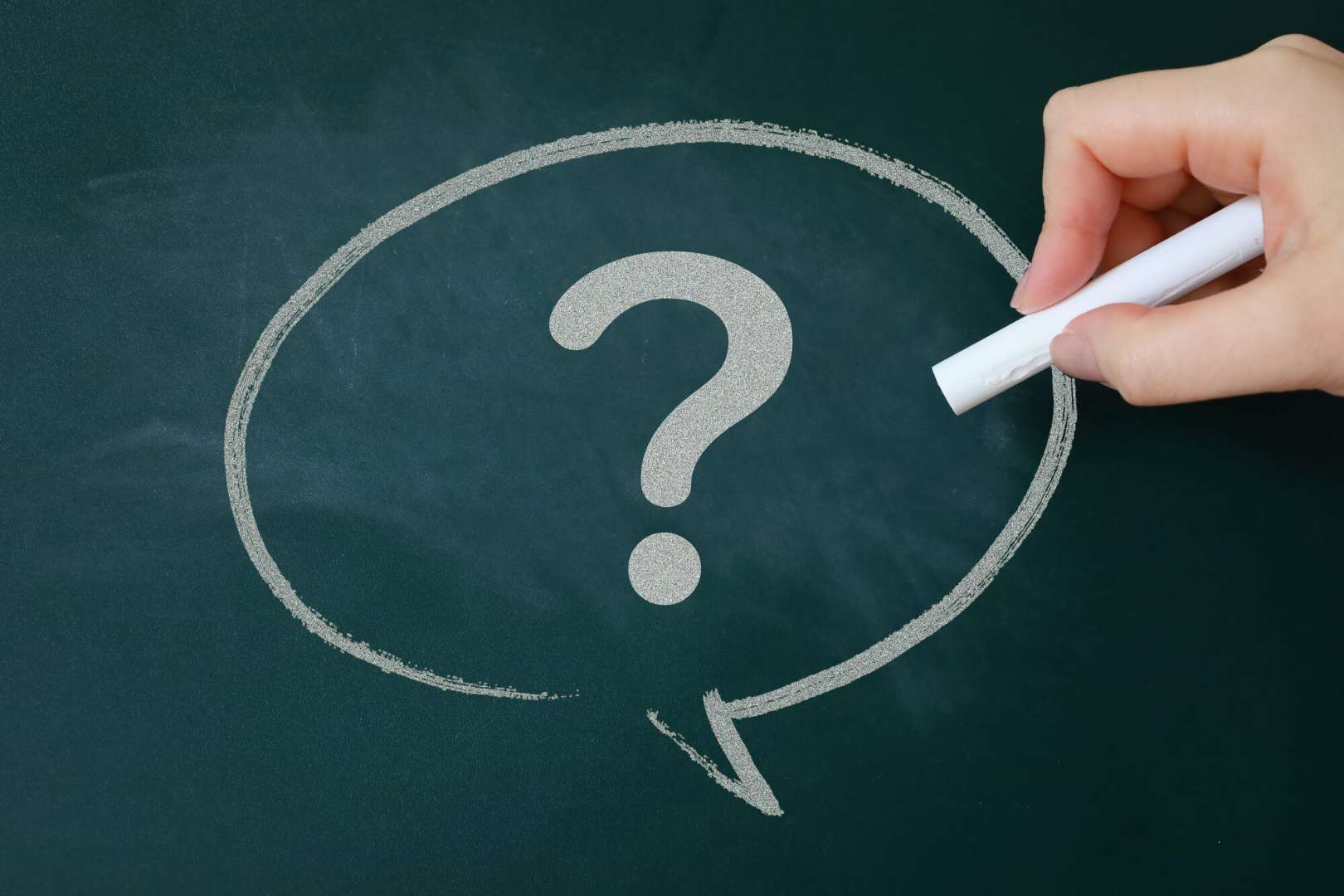
キッチンに収納を後付けする際、見た目や収納量ばかりに目がいきがちですが、実際に使うときの快適さを左右するのは、サイズ・配置・素材の3点です。まずサイズについては、設置予定のスペースに対して「ピッタリすぎる」家具は要注意です。壁や床の微妙なゆがみ、巾木の存在などで、思ったように収まらないことがあるからです。数センチの余裕を持たせて設計することが大切です。
次に配置。これは動線との関係が最も重要です。たとえば冷蔵庫やシンク、作業台との位置関係が悪いと、収納の中身を取り出すたびに回り道をする羽目になります。使用頻度の高いものをどこに収めるか、扉や引き出しを開けたときに他の動作の妨げにならないかをしっかり考えておきましょう。
そして素材。キッチンは水や油を扱う場所なので、表面の耐久性や掃除のしやすさも無視できません。見た目の好みだけで選ぶと、後々のお手入れが大変になることもあります。
このように「使える収納」にするには、見た目以上に実用性に目を向けた設計が必要です。見えないところの配慮こそが、満足度を大きく左右します。
既製品だけでは収まらない…と感じたら
既製品の収納家具は、手軽さという点では非常に優れています。手ごろな価格で購入でき、すぐに設置できるのは魅力です。ただし、キッチンのように設備が多く、空間が限られた場所では、「置けるけれど、しっくりこない」という状況が起こりやすいのも事実です。
たとえば、冷蔵庫と壁の間にちょっとしたスペースがある場合、「ちょうど良い棚が見つからない」「奥行きが合わない」「高さが中途半端」といった悩みが出てきます。そうしたときに、既製品を無理に合わせようとすると、結局使い勝手を犠牲にしてしまうことになります。
一方で、オーダー家具や造作収納なら、間取りや使い方に合わせて一から設計できるため、無駄のないスペース活用が可能になります。特に、ゴミ箱や炊飯器などの“見せたくないけれど頻繁に使うもの”の収納には、設計段階での工夫が欠かせません。
ただし、オーダー家具にも当然デメリットはあります。コストが高くなりがちで、完成までに時間もかかります。そのため、必要な収納量や使い方の優先順位をしっかり整理したうえで、既製品とオーダー品のバランスを取ることが現実的な選択肢となります。自分の暮らしに合った収納のかたちを、無理なく見極めることが大切です。
実際にどんなキッチンに、どう収まる?
キッチンの背面収納は、住まいの間取りや家族構成、生活スタイルによって最適な形が大きく異なります。事例を見ると、限られた幅の中でも引き出しを細かく分けて収納量を確保したり、炊飯器や電子レンジを収納内に組み込んで生活感を抑えたりと、工夫次第で見た目と実用性を両立していることがわかります。
また、天井まで届く高さの収納にすることで、空間を無駄なく使っている例もあります。このようなケースでは、上段には季節ものや使用頻度の低い食器を、下段には日常使いの道具を配置するなど、使い分けの視点が活かされています。扉を引き戸にすることで動線を妨げず、省スペースでの使い勝手を高めている事例もあります。
一方で、視界が抜ける背面収納を選ぶことで、空間に圧迫感を与えない工夫をしている例もあります。キッチンの広さが限られていても、視線を遮らない工夫や奥行きの抑制によって、スッキリとした印象を保つことが可能です。
収納とは、単に“モノをしまう場所”ではなく、“暮らしやすさ”を支える存在です。事例を見ることで、「自分の家にはどういった収納が合うのか」「今の不便さは何が原因なのか」を見つめ直すヒントになります。
収納の形に正解はありませんが、日々の使い勝手を丁寧に考えることで、納得できる選択肢が見えてきます。
「ただ置くだけ」と思っていませんか?
キッチン収納の後付けにおいて、家具選びよりも重要なのが「空間全体をどう活かすか」という視点です。収納単体ではなく、キッチン全体の使いやすさ・見た目・動線を含めて設計できるかどうかが、後悔を防ぐ最大のポイントになります。
たとえば、冷蔵庫やシンクとの距離感、ゴミ箱の配置、家電のコード取り回しなど、ひとつの収納を足すだけで連動して見直さなければならない要素は意外と多いものです。既製品を持ち込んで配置してみたら「意外と扉が開かない」「キッチンワゴンとぶつかる」といった声はよく聞かれます。
収納選びは、家具単体ではなく“空間設計”のひとつと考える必要があります。実際、収納家具の設計を得意とする工務店や家具工房では、収納する物の種類や家族の動き方、掃除のしやすさまで考慮しながら、空間全体の流れを崩さない設計を行っています。
こうしたプロの視点が入ることで、単なる“置き家具”では実現できない細やかな配慮が可能になります。将来的な使い勝手や見た目を含めて納得のいく選択をしたいなら、収納と空間の関係を踏まえた提案ができる専門家に相談する価値は十分にあります。
空間設計の視点から収納を見直したい方へ:
https://www.kaneko-knst.com/aboutus
後悔しない収納をつくるために、まず確認したいこと
キッチン収納の後付けは、ほんの少しの思慮不足が、日々のストレスにつながることもあります。逆に言えば、数点の基本を押さえておくだけで、後悔のない選択ができる可能性がぐっと高まります。
まず、自分の生活スタイルに合った収納量と収納方法を把握することが大切です。「とりあえず入るから」と詰め込む収納ではなく、何を・どこに・どの頻度で使うのかを棚卸しすることで、本当に必要な構成が見えてきます。
次に、設置予定のスペースを正確に把握し、必要があればプロに現地確認を依頼しましょう。床や壁の微妙な傾き、コンセントや照明位置の制約など、図面では気づきにくい要素が実際には多くあります。
そして最後に、「見た目」と「使いやすさ」のどちらを重視するか、自分なりの優先順位を持つことも重要です。どちらも完璧に、というのは理想ですが、スペースや予算には限りがあります。何を一番大事にしたいかを明確にすることで、選択に迷いがなくなります。
収納は、一度設置すると簡単には動かせないからこそ、丁寧な準備と判断が求められます。
もし収納について相談したいことがあれば、控えめながらこちらの窓口もご活用いただけます:


